大器晩成について
人生も同じだぞ、という北方節
夢というテーマで記事を書いていますが、今回は作家北方謙三先生を題材に「大器晩成」ということについて触れます。夢にも色々な種類があり、叶えるまでのパターンがいくつかありますが、今回のは長い時間をかけて掴む夢についてです。
夢の中には、例えば30歳位までに見切りをつけないといけない、年齢制限のあるものがあります。プロ野球やJリーグの選手などのスポーツ系、弁護士や医師などの資格系など免許取得までに時間のかかるものなどがあります。その点文筆業は比較的プロになってからの寿命が長いと言われていて、もちろん職業作家として書き続けられている人のことを対象としています。
そして文壇では、50歳の作家でもまだ若手と言われたりします。遅咲きの作家は何人かいますが、その中でも一番興味をそそられるのは北方謙三先生です。
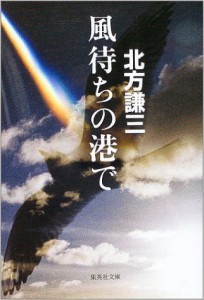
※北方謙三『風待ちの港で』より引用して文章を構成しています。
【北方謙三略歴】
昭和22(1947)年、佐賀県唐津市生れ。47年中央大学法学部卒。58年「眠りなき夜」で第1回日本冒険小説協会大賞、第4回吉川英治文学新人賞、平成3年「破軍の星」で第4回柴田錬三郎賞、16年「楊家将」で第38回吉川英治文学賞、18年「水滸伝」で第9回司馬遼太郎賞、19年「独り群せず」で第 1回舟橋聖一文学賞、22年第13回日本ミステリー文学大賞を受賞「BOOK著者紹介情報」より。25年紫綬褒章を受賞。
ご覧の方の中にはHOT DOG Pless『試みの地平線』というお悩み相談のコーナーでお馴染みのハードボイルド作家として記憶しているかもしれません。私は結構ガチで作家北方謙三の作品もさることながら、その生きる姿勢を尊敬しています。作家になるという夢を叶えて、さらに作家で居続けることに誰よりも執念を燃やした作家と言えます。
そして、本人曰く「作家として生き続ける現実さえあれば、その他は全て虚で構わない。本を売る為に、認知してもらう為にテレビのクイズ番組に出て「ハイ」と手を挙げることなんて虚だから何とも思わない。」と。
【北方謙三同窓会へ行く】
「出版社へ原稿を持ち込み、10年間北方は一度も同窓会を欠席したことがなかった。初めのころは大学を卒業して一流企業に就職して高給取りになったヤツが座の中央でグラス片手にそっくり返って高笑いしていたのに、数年経つと、片隅に引っ込んでいたりする。代わりに、あまり聞いた事のないような会社に就職したヤツが会社の隆盛とともに中央にしゃしゃり出て、高笑いしている。会社の隆盛と社内での昇進との複合で、同窓会の主役が交代しているのだ。
そこで、「北方何してる?」と聞かれ「まだ小説書いてる」「・・・そうか、偉いな。。」と蔑みと侮辱と哀れみが混じっていても、キレて暴力的になるよりも屈折した自虐性のほうが快感だったりもした。」【風待ちの港でより引用】
【才能との決着】
作家の入り口としては、学生時代に書いた小説『明るい街へ』が「新潮」の同人誌推薦号に載った。そのことがその後10年にも及ぶ苦闘の始まりだった。
北方謙三は、大学を卒業したばかりの頃は自分の才能に少しも疑問を持たずにいた。その頃の同世代の作家には、中上健次を筆頭に立松和平、津島佑子、金井美恵子達がいて、その彼らと比べても、自分は天才だと思っていたそうだ。作家にとって夢を叶えるためには「世の中に受け入れられるかどうか。」が重要なファクターとなります。
そんなこんなで、5年経っても中々世間に受け入れてもらえずに、もしかすると本当は自分には才能がないのではという思いに苛まれ、さすがに気持ちが揺れてきたそうです。北方謙三はその10年の間に書いた原稿が楽に自分の背丈を超える程だったらしいです。しかも一字一句精魂込めて書いて。その間100作書いて活字になったのはたった三作。10年間でたったそれだけだったらしいです。

※本当に雲を掴むような夢への道のりです。
【北方謙三の努力】
北方謙三は20代前半で結婚していて、小説を書きながら奥さんを養っていかないといけない状況だった。奥さんは教師をしていたが、結婚と同時に退職してしまい、北方は奥さんの収入をあてにできない為、港へ行き沖仲仕をやったりゴミ収集車の後ろに立ってゴミを収集したりしていた。それでもエネルギーの大半は小説に注ぎ、1ヶ月の生活費にも事欠くような状況になっていた。
その時の北方は「とにかく35歳までやって芽が出なかったら諦めることに決めていた。」という。そう決めることで肚をくくり、エネルギーをマイナスに向けるのではなく、あくまでプラスの方向に向けるように努めた。とかくくすぶり中はネガティブな感情が湧きがちで、その不安を解消する為にギャンブルなどに手を出し夢どころか人生自体も持ち崩してしまうこともある。夢とはキラキラとしていて前向きなエッセンスに満ちたエネルギー体という面以外に人生を駄目にしてしまう麻薬のような側面もある。
北方謙三は純文学を書いていて、(※純文学の説明は他のサイト等にゆずるとして)純文学作家はどちらかといえば人間の内面を描く芸術家として認識される。北方の同世代で中上健次という純文学作家がいる。彼には北方が持ち得ない、自分のオタクの中の地獄のような心情を拾い上げる才能があった。そしてそれを芸術作品にまで仕上げるエネルギーがあった。その差がどうしても埋まらない。
「中上健次が持っているものに、どうにもならない嫉妬を感じた。自分がどうあがいたところで、中上健次が持っているものは持ちえない。自分は本当に天才なんだと信じて芸術家を志してやってきたが、もう芸術家と呼ばれることは諦めるしかないと思った」「本当に天才なんだと信じて芸術家を志してから、実はダイアモンドでもなければ金でもなく、要するに自分は川原に転がっている砂利の一個にすぎないというふうに思うまで10年。さすがにそれだけの時間を棒に振ってしまったという思いは堪えがたくあった。そこらに落ちている石っころにすぎないという苦い自覚が喉元から臓腑に落ちていく。すると、遠い先まで自分の人生が想像された。」『風待ちの港』より
【純文学を諦めエンターテインメントを書きようやく作家として活躍】
北方謙三はいったんは辞めようと思った。しかし、10年間、腕は磨きに磨いた。これに関しては誰にも負けないという自負があった。それだけの努力をしてきたという自信があった。だったら、内面の暗さだのなんだのへのこだわりを捨て去って、本当に書きたいものを書いてみよう。そう思った。たしかに、10年やってきて、結局、その辺の川原の石っころにすぎなかったが、10年間磨いてきた腕は捨てたもんじゃない。石は石なりに結構光るぜという強い自負心があった。その光を世間に見せてやらなければ、おさまりがつかない。10年間、青春をやりつづけて自分に落とし前をつけなければ、どうにも肚が収まらなかった。これで駄目だったら小説を辞めると決めて、吹っ切れたようにエンターテインメント小説をのびのびと書き、編集者のところに持ち込む。
結果、100枚を超えるエンターテインメント小説は、かつて「新潮」に掲載された『明るい街へ』をこれまでに培った力で、さらに物語として拡充した内容だった。編集者の同意と評価を受け、最後の最後に本の販売に漕ぎ着けた。
「人生というのは、かならずしも努力が正当に報われるものではないと思う。どんなに努力しても、運、不運、というものに左右される部分がある。たまたまヘミングウェイの短編小説が好きで、その中に出て来る「バッタが黒かった」という一場面が最後に引き上げてくれた編集者と意気投合した縁が小説家・北方謙三を世に送り出してくれたという経緯があった。もし彼とバッタの話をしていなかったら、はたしてどうなっていたか、そう思うと本当にきわどいところをすり抜けたという気持ちがある。」と本の中で語っている。
そうして、北方謙三は年間10冊書く様な売れっ子人気作家への階段を登っていく。しかし、たまたま運が良くてデビューしたとしても、その後ヒット作が無く消えていく作家はごまんといる厳しい世界の中で、北方謙三は彼らと違う必死さで努力を続けた。「いったん掴んだ運を離さずに、大きくしていこうとする努力をした。たまたま手にした運を開かせるには、努力と才能がいる。
どちらもそれまでの蓄積が問われるのだ。ぼくの場合は10年間、表現を削りに削り、言葉を選びに選んで腕を磨くという努力を重ねてきた。10年努力して、やっと本が出た。だから、死んでもこの運を放すまいという気持ちが人一倍あった。絶対に放さないぞと飛びついて、石に噛み付くようにして、その運を大きくしていこうと必死で頑張ったのだ。結局。成功するかしないかかは、運、不運なのではなく、たまたま手にした運にどこまで食らいついていけるのかだと思う。」『風待ちの港』より
北方謙三は長い修行時代を経て、30代半ばで作家デビューを果たし、その後作品を書き続けるという挑戦を続け、数々の賞を得る大作家へと登っていった。その仕事ぶりや実績を支えているのは、見た目のワイルドさや自由奔放なイメージとは逆で、作品へと投下される真っすぐで堅実な仕事ぶりと、どんなことをしても作家を続けていくという意志だと思える。
彼には大器晩成という言葉がよく当てはまる。

糸井重里さんが過去にこんなことを言っていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大器晩成ということも信じないわけではない。
つまり、大器晩成と言われるような人は、「立ち合い」の時期が遅いのだ、と思っている。
周囲が勝負に出始めた時にまだ、ぶらぶら遊んでいるのではないか。
みんなが、あいつは強くないと考えているときにはまだ彼は勝負にも参加していないのだから、勝ちも負けも、強いも弱いも知りやしない。
で、たっぷり力量がついたころに、よいしょっと力強い立ち合いをして、試合のイニシアティブをとるんじゃないかな。なんて思っているのだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
北方謙三、浅田次郎、山本一力など、遅咲きの作家のその後の活躍は周知の通り。世にでる前に、しっかりと自分の武器を増やし、世の中や人間を見、あるいは場の雰囲気を事前に見ておくなどの準備ができている。それ以前を助走と考えると、いざ勢いがつき始めたら面白いですよね。
先に走っていた人は、手持ちの武器を使い果たし、あるいは摩耗し、疲れが見えている頃に、遅咲きの人はぎゅいーんと力強く抜き去って行く。
人生の勝負は、野球でいうと9回では終わらない。
何回でも、100回でも、まだまだだと思っていればまだまだ。
私は強くなれただろうか?たっぷりと力量がついただろうか?
遅くなったけど、その勝負をはじめよう。
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/harunaga/www/html/wordpress/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

コメントを残す